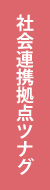学生相談(カウンセリング)の利用
学生相談室は管理研究棟1階(保健室内)にあります。学生相談室には臨床心理士が曜日及び時間を定めて在室しており、学生の様々な相談(カウンセリング)に応じています。
例えば「友だちのこと」、「大学のこと」、「自分自身のこと」、「特に悩みはないけれど、話しをしてみたい」、「一人で悩みを抱えてしまって誰にも言えない、一人では解決できない」など、どのようなことでもかまいません。また、障害のある学生からの相談にも対応しています。どのようなことでも、気軽に相談してください。
ただし、臨床心理士への相談は事前予約を原則としていますので、学生支援センターで予約してください(学生支援センターで直接予約するか、E-Mail:hoken@nuis.ac.jp宛に学籍番号・氏名を明記して予約申込をしてください)。なお、当日予約が入っていない場合は相談ができます。
また、学生会館内の学生支援センターには学務課職員(看護師)がおり、学生の様々な相談に対応しています。どのようなことでも気軽に相談に来てください。
学生支援センターでの相談は予約不要ですが、授業などの都合に応じて時間を予約することもできます。
臨床心理士の相談日・時間:
授業期間中の月曜日(隔週 /15 時から 18 時)または水曜日(月 1 回 /15 時から 18時)
(要予約)
※曜日によって、対応する臨床心理士は異なります。
※詳細はポータルサイト及び掲示で確認してください。
学生支援センターの相談日・時間:
月曜日~金曜日の 9時から 18 時まで(予約不要)
※詳細はポータルサイト及び掲示板で確認してください。
保健室は管理研究棟1階にあります。風邪、腹痛などの体調不良や体育実技などでの負傷、その他心身に不調をきたした場合は保健室を利用することができます。保健室の利用を希望する学生は、学務課まで申し出てください。
毎年、所定の期日(4月上旬)に学生の定期健康診断を実施します。この健康診断は全学生が毎年、受診しなければなりません。また、必要に応じて臨時に行うことがあります。その結果、特に所見のあった学生には、再検査、精密検査、保健指導を行います。
定期健康診断を受診していない学生には、健康診断証明書を発行することができません。
なお、本学の学生定期健康診断(結核定期健康診断)は、新潟市結核予防費補助金事業に基づく補助金を受けて実施しています。
大学において予防すべき感染症について
大学において予防すべき感染症は、学校保健安全法施行規則で下記のとおり規定されています。大学内で一人でも感染者が発生すると大学内外での影響が大きく、当該感染者一人だけの問題ではなくなります。また、それぞれの感染症には登校できない期間が定められていますので、各自が予防接種を受けるなど感染予防に努めるとともに下表の感染症と診断された場合は速やかに学務課へ連絡してください。
また、登校を再開する際は、ポータルサイトから、「学校感染症治癒証明書」をダウンロードして医療機関に記入してもらい、出席停止期間を証明できる書類として学務課へ提出してください。
| 感染症の種類 | 登校できない期間 | |
|---|---|---|
| インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで | ただし、医師より感染の恐れがないと認めたときは、この限りではない |
| 新型コロナウイルス感染症 | 発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
| 麻しん(はしか) | 解熱後3日を経過するまで | |
| 流行性耳下腺炎(おたふく風邪) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
| 風しん(三日ばしか) | 発疹が消失するまで | |
| 水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化する(かさぶたになる)まで | |
| 咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
| 髄膜炎菌性髄膜炎、結核、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎(はやり目)、急性出血結膜炎、その他の感染症 | 医師より感染の恐れがないと認められるまで | |
性感染症(STI)
10歳から20歳代の若者を中心に、性感染症(STI)が増えています。症状が現れにくいSTIもあるため、本人が気付かないうちに感染している可能性もあります。そのため、気付いた時には重症になっていたり、相手に病気をうつしてしまうこともあります。自分の体のことや将来のことを考え、気になることがあったらすぐに医療機関を受診しましょう。また、学生支援センターでも相談を受け付けます。
※相談者のプライバシーや秘密は守られます。
本学では下記の4箇所に自動体外式除細動器(AED)を設置しています。AEDは自動的に心臓の動きを解析し、除細動が必要かを音声で指示する機械で、資格を持つ医療従事者以外でも、使用することができるようになっています。
人命救助に必要な行動が迅速に、途切れずに行われることを「救命の連鎖」といい、①119番への通報、②人工呼吸と心臓マッサージの実施、③AEDの使用、④医師または救急隊員による救急処置の、一連の実施によって成り立っています。
学内外を問わず、意識がなく倒れている人がいたら周囲に協力を求めるとともに、救命手当てにあたって下さい。
自動体外式除細動器(AED)の設置場所
【本校(みずき野キャンパス)】
・管理研究棟正面玄関前
・体育館棟玄関
・情報センター棟図書館入口
【新潟中央キャンパス】
・事務室(2階)
健康保険の利用(遠隔地被保険者証)
保険証が被扶養者一人に一枚発行されていない場合、自宅外通学の学生が健康保険を利用するためには、遠隔地被扶養者証が必要になります。扶養者が所属している健康保険組合や共済組合へ申請し、遠隔地被扶養者証を発行してもらってください。
学生教育研究災害傷害保険(学研災)
この保険は大学の教育研究活動中の急激かつ偶然な外来の事故により、身体に傷害を受けた場合の救済措置として加入する保険です。大学では入学時に全員加入となっています。
教育研究活動中とは正課中、学校行事中、大学施設内にいる間(ただし、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間または大学が禁じた行為を行っている間を除く)、大学施設外での課外活動中を言い、通学中、学校施設等相互施設間の移動中も保険金支払の対象となります。ただし、通学、学校施設等相互施設間の移動を車で行う場合は、駐車場使用許可願の提出がないと保険金支払の対象とならないので注意してください。
これらの活動中に傷害を受けた場合は、直ちに学務課へ事故の届出を行い、所定の手続きを取ってください。なお、詳しい内容は、新入生ガイダンス時に配布の「保険のしおり」を参照してください。
学研災付帯賠償責任保険(学研賠)
学研賠は国内において、学生が正課・大学行事およびその往復中で、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したことにより被る法律上の損害賠償を補償します。本学では任意加入となっており、加入の窓口は学務課です。
対象となるのは正課・大学行事およびその往復中、インターンシップ、学外実習、ボランティア活動およびその往復中。但し、大学が正課・大学行事・課外活動と認めた場合に限ります。保険の対象となる事故を起こした場合は学務課に申し出てください。